

前年に引き続き「時を経ても残るもの」をコンセプトに、写真家それぞれの若い時に撮影した写真、子供の頃の写真などの展示します。

4歳のときのアルバム。父が主催する舞踏グループ「天使館」の生徒たちと伊豆高原の合宿に行ったときのひとコマ。まったく記憶がないが、キャプションによれば、このときぼくは初めてカメラを持ち、シャッターを切ったらしい。ヘタクソな写真である。が、構図が相変わらず斜めっているのは、あの頃からなのか、と驚く。

私が被写体となった写真です。3歳か4歳のはずです。撮影者は父でしょうか。
いまから36、7年前のプリントです。

20歳前半から約10年間、35ミリ白黒フィルムで日本全国の島や半島を撮影していました。当時はスタジオ、出版社のカメラマンとして勤めていたので、短い休暇を利用してはひとり旅を繰返していました。モノクロでの表現に限界を感じていた頃、アメリカの「ニューカラー」作家の写真集に興味をもち、大型カメラを使い、ネガカラーフィルムからオリジナルプリントをする手法に作品撮りは変化し、白黒は止めてしまったので、若い時の写真を見ると、瞬く間に通り過ぎる夏を、ひたすら歩き写真を撮っていたことを思い出します。

46年前、人生とか社会とかまだまだわかっていなかった多感な頃、胸の震えだけで真っ直ぐ突き進んでいた24才の自分がいた。そんな時期に撮ったこの原爆被爆者の写真は、僕にとって写真の奥深さや難しさを教えてくれるきっかけとなった1枚で、単に懐かしいとは言い切れない、そして戦死した父親ともだぶる大切な写真でもある。

アシスタントの頃、中国の市場の中で撮影したものです。カメラはローライフレックスF3.5。ネガも露出が足りずに薄く、暗部が浅いですが、初めての海外ロケでアシスタントだったため焦って撮影したからだと思われます。とても賑やかな市場の中で水槽の周りだけがひっそりとしており、吸い寄せられるように撮 影しました。

父の若い頃の趣味はもっぱら写真であった。85才を過ぎた今ではカメラを手に持つことも全くなくなったが、僕が幼少の昭和30年代頃には3つ違いの姉と僕 をあちこちに連れ出しては2人の遊ぶ姿をカメラに収めていた。当時暗室作業も自分でやっていたのだが、会社員だった父には当然暗室もなく、6畳の和室を閉 めきって真っ暗にし、赤い電球をスタンドに灯して何やらごそごそやっていた。僕自身は大学で写真の授業を受けるまではほとんど写真を撮らなかったのですぐ にはその記憶と結びつかなかったが、写真家を生業としてやっている現在の自分を考えると、暗室で作業する父の姿が幼心にどこかインプットされ何かしら影響 されているのかなと、感じる日々である。その頃の古いプリントを見ると、写真には姿形だけでなく、その時々の空気や家族のストーリー、親の愛情といったも のが濃密に写り込むものだということが良く解る。

息子の元彦はいま24歳。すでにカメラマンとして自立して頑張っている。その彼も、僕の中ではまだまだ子供のイメージが抜けない。当時、国分寺に住んでい た。僕はカメラマンになるぞと、毎日がテスト撮影とプリントの日々だった。被写体はほとんどが元彦と長女の麻乃だった。学校から帰ってきてすぐに自転車で 遊びに行くと夕方暗くなるまで全く帰ってこない。そしてやっと帰ってくると、泥だらけ。しかしその表情がよくてトライXを増感して撮っていた。妙に古臭く て昭和の香りがする写真だ。そう思うとフィルムにはちょっとノスタルジックな香りを感じる。フィルム写真は20世紀から21世紀にまたがって生きる僕ら の、束の間のロマンチックな夢だったのかもしれない。
 左 :「『1970年20才の頃』より 青山道りのジグザグデモ」1970年
左 :「『1970年20才の頃』より 青山道りのジグザグデモ」1970年
右 :「『1989年 東欧真冬に咲いた花』より 革命前夜のバーツラフ広場」1989年
1970年、僕が20歳の頃。沖縄返還を要求する学生デモ。そして、1989年、プラハでの民主化を訴える民衆のデモ。カメラはいつも出来事を伝える目撃者。写真家になって良かったと思う。

小さいとき、家の写真館が忙しくてかまってもらえなかった僕が堂々と母にかまってもらえた瞬間。

近所の浜辺を写したり、大学周辺ではカメラを向けた機動隊やデモ隊から追い掛けられたり。自己流で写真を始めて一年も経っていなかった頃、見知らぬ処で写 真を撮してみたくなり、筑豊に2ヶ月余り居た事があった。九州の衰退した炭坑の町に特別思いがあった訳でもなく、知識もないまま毎日、朝から暗くなっても 歩き回っていた。美術家の菊畑茂久馬さん、民衆の作家上野英信さん、明治、大正、昭和と炭坑夫の生証人であり絵師の山本作兵衛翁らと知りあう事が出来、今 でも付合いを続けている大切な友人とも出会った。大勢の個性強烈な人達から21才の僕は親切と刺激を受け、貴重な財産として奥底に今も在る。当時の稚拙な プリントを眺めているとカブリやシミ、変色も含めてそこには、その頃の僕が居るように思える。

この写真は10年前に初めてひとつぼ展に入選した写真の中の一枚です。当時はまだ写真を始めてから1年程しか経っていなくて、目に見えるもの全てが面白く見えて、がむしゃらに撮影していました。今、ライフワークになっている夜の撮影もこの頃が原点になっています。この頃の作品を見ていると、少し気恥ずかし い部分もありますが、高校生当時の新鮮な気持ちが蘇ってきます。今の思いを忘れない為に、写真に限らず何か形に残しておく事が大切なのではないかと思います。

『遺影』
島根に住む親父が亡くなったその後、残った家を他人に貸すため家財道具等を全て処分していった時、自分が引き取ったものの中に、仏間に飾ってあった先祖の 遺影があった。実はこの写真の女性がどういう人で何故若くして亡くなったかなど何も知ってはいないのだが写真館で撮られたであろうこの写真を僕はとても良 い写真だと思ってながめている。

このアルバムの1ページを選んだのは、撮られた時のことを僕が覚えているからだ。撮影したのは父・藤塚米太郎。父は1898年生まれの「19世紀の人」で ある。撮ったのは昭和19年だから、6男の僕は5歳。父と母・千代には8人の子供が生まれ、新聞社に勤める父は写真が趣味だった。撮影対象はほとんど家族 だったらしく、その他の写真は見当たらない。当時、港区芝の家は溜め式のボットン便所だった。父は節穴や板の継ぎ目に黒紙を張り、光を遮断して便所を暗室 にしていたのである。写真を見ると4×4センチのベスト判で、撮影したカメラは憶えていないが2眼レフだったと思う。僕は銀座の帰りに飛行機と覗きカメラ を買ってもらって、両手に宝でご機嫌だった。思えば、長男次男ならともかく、6男の僕や7男の弟まで、わが子とはいえ、よくも撮影していたものだ。解説も 父の懐かしい筆跡である。ネガの整理番号まで書いているのだから
 左 :「お爺ちゃん、お婆ちゃんと私」1971年
左 :「お爺ちゃん、お婆ちゃんと私」1971年
右 :「私」1971年
この写真は父が撮った写真です。父はアートディレクターであり、私にモノを創る心を教えてくれた師でもあります。いまから37年前に0才の私が父に撮られ た写真(フィルム)は現存しており、そのフィルムはまさかそこに写っている被写体にプリントされるとは思ってもみなかったでしょう。私が写真家にならなけ れば起こり得なかったでしょう。父は自分の寿命が短いと悟ったときにこのフィルムを私に手渡しました。この写真を見ていると色々な事が思い出されます。到 底一言では書ききれません。沢山の事柄を語りかけてくるのです。父の撮ってくれた写真、この写真を自分の子供に孫にと伝えて行きたいとともに私が写真家と して撮らせていただく被写体の方々に私が父からもらった暖かみと同じものを残していけるよう努力精進して参ります。下の小さい写真が37年前当時にプリン トされたもので、上の大きい写真は私がプリントしたものです。ネガは若干ノリの薄いものをILFORD WARM TONE の2号で柔らかくプリントした後にファーマー式減力で所々ハイライトをたたせ、その後、ネルソン金調色を施しアーカイバル処理をしたプリントです。

1974年の作品で、一番最初の展覧会に使った写真です。約35年前撮影したものですが、私の中では5、6年前の気分です。
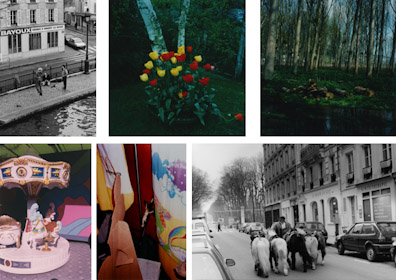
すべて、自分が、写真を撮り始めたころのもので、そのころはあらゆるものに興味があり、無闇にシャッターを切っていたように、記憶していたが歳月がたってもう一度見たとき、今の自分のやっていることと何も変わらない、それが写真なのかも。
![]()
Copyright© 2006 - 2015 Gelatin Silver Session All Rights Reserved.